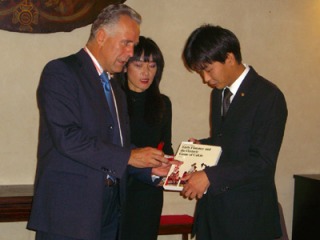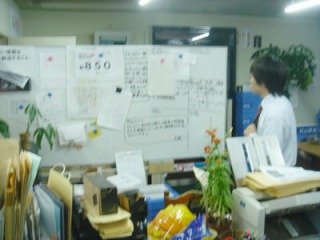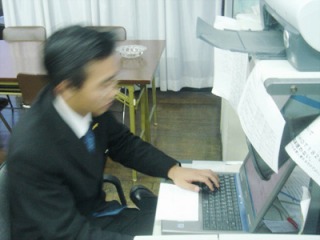委員長(柴田章喜)
ただ今から、財政総務委員会を開会致します。本日は、各局の理事者からの報告案件はございませんので、所管局に対する一般質問を行います。
それでは、質問のある方はただ今挙手いただき、あらかじめ局名と質問内容をお申出いただきますようお願い致します。
村山 祥栄
私の方は、総合企画局に対してホームページのウエブアクセシビリティについてと、総務局に対して広告料収入の問題について、2点お尋ねしたいと思います。
村山 祥栄
私の方は、京都市情報館について御質疑をさせていただきたいと思います。ここ数年、京都市情報館のホームページがかなり充実をして参りまして、結構他都市と比べてもかなりすばらしいホームページをお作りいただいていると思っております。
そこで、何点かお尋ねしたいんでございますけれども、一つは、2004年に高齢者・障害者等配慮設計指針という
JIS の指針が出されたと思うんですが、それに伴いまして、ウエブアクセシビリティを、ウエブの使いやすさとか利便性をどうしていくのかということが一つ大きなテーマになってきていると思うんですが、このウエブアクセシビリティについて、京都市情報館は具体的にどういった取組をされているのか、また、これに関してどういう御認識をしていらっしゃるのか、まずお尋ねしたいと思います。
市長公室長(塚本稔)
ホームページのウエブアクセシビリティ、だれもが年齢や障害に関係なくホームページにアクセスできると、こういうことにつきましては、京都市のホームページの大きな方針として、一昨年の7月、そして昨年の2月にホームページを充実致しまして、音声の読上げであるとか、文字の拡大、そしてまた配色の、色ですね、色の変更サービスというのを実施しております。
村山 祥栄
ありがとうございます。
音声の読上げに関しては、非常に大切なことだと思います。特に視覚障害者は音声の読上げソフトしかございませんので。
私も今日、総務省のページとか京都市のページで、音声で読上げソフトをちょっと見ながら、ああ、なるほど、こうして読上げをしているんだということを見ていたんでございますけれども、私自身が今回問題だと思っておりますのは、これを、京都市だけの問題ではないんですが、これから各自治体が取り組んでいかなければいけない問題の一つとして、PDF
ファイルをどう取り扱っていくのかと。
逆に言いますと、PDF ファイルとか画像というのは、音声システムに対応できないソフトでございますので、具体的に視覚障害者の方が読上げをしたいなと思っても、読上げができない状況にあるのが現実だと思っております。
この件につきましては、総務省の情報通信政策局ともお話をさせていただいたんですけれども、総務省としても何とかこれをやっていきたいという思いはお持ちだけれども、なかなか各自治体が取組が進んでいないのが正直現実ですと。
また、作る方にとって、非常にPDF というのは便利なものでございますから、どうしてもそちらの方に傾斜してしまっている傾向があるんじゃなかろうかという風におっしゃっていました。
ただ、聞いていますと、今、みんなの公共サイト運用モデルということで、地方自治体の職員向けに、総務省なんかもこれをどんどんやっていきましょうということで、研修なんかも随分やっておられるようでございます。
そういったものを使いまして、今後こういったPDF からテキストファイルに各局の情報を移行させていくというお考えというのはないんでしょうか、あるんでしょうか。その辺を含めてちょっと御見解をお伺いしたいと思います。
市長公室長(塚本稔)
先生のPDF ファイルの件でございますが、インターネットのホームページというのは一番の特性は、大量の情報を、24時間最新の情報を発信するということにあるかと思います。ただ、その点、職員がホームページの更新とか新規のホームページを作成するに当たって、PDF というのは非常に簡単、迅速にできるという特性を持っております。
ただ、一方で、先生御指摘のように、音声の読上げソフトにうまく対応できないというそういう面もありますので、先ほど申しましたように、一方で、大量の情報を迅速かつ最新の情報を発信するという側面と、もう一つは、年齢に関係なく、障害の有無に関係なく、だれでもホームページにアクセスできるというそのアクセシビリティ、その両方の側面をいかに調和してやっていくかと、これが大きな課題かと思っております。
村山 祥栄
ありがとうございます。
多分そのとおりだと思います。実際使い勝手が非常にいいですし、変換がすごく楽なので、ボタン一つでPDF
に出来ちゃうというメリットはやっぱり非常に大きいと思います。ただ、色々聞いていますと、慣れてくると、ほんの数分でこのPDF
じゃなくて普通のテキストに変換する方法が出来ていますということで、慣れるまで少しお勉強をしていただかなくてはいけないんですけども、ある程度慣れてくると、かなり迅速にその辺の作業も進むようになってきていると伺っております。
実際その視覚障害者だけじゃなくて、かなり古いパソコンをお使いの方であるとか、いまだに、私もこうしてつないでいるときはいいんですけども、外に持ち出したりすると、いわゆる携帯用モデムなんかを使いますと、やっぱり非常に速度も遅うございまして、そういったものではやっぱりPDF
を見ようと思っても、めちゃくちゃ時間が掛かってしまうと。
実際いかに迅速にファイルを開けるかどうかというのが、やはり見る側にとっては大変重要なかぎになってきますが、あまりちんたらしていますと、面倒くさいから閉じてしまうというようなことが多々あろうかと思いますので、できれば、今すぐにというわけにはいきませんけども、少しずつ、京都市情報館が中心になって、皆さんが始めていただければ、少しずつ各局にもそういった流れも広がってくるでしょうし、皆様の方から始めていただかないと、いつまでたっても折角音声読上げソフトまで入れていただいているのに、有効に活用できないままということになりかねないので、是非ともこれについては御検討いただいて、できれば早く御対処をいただきたいなという風に思っております。
市長公室長(塚本稔)
ホームページの作成につきましては、職員に対する研修の充実、それから簡単にホームページが作成できるようなそういうシステムの導入についても今後検討して、PDF
という利点と欠点、両方兼ね備えておりますので、PDF に変わってHTML 化ということでファイルを作っていくということについても検討して参りたい、こう思っております。
村山 祥栄
是非よろしく御検討お願い申し上げます。
それと、もう 1点、話は変わるんですけど、ウエブページ、要は、ホームページにバナー広告を、昨年から取組を始めていただいていると思うんですが、現在のところ、バナー広告の収入というのはどれぐらいになるんでしょうか。
市長公室長(塚本稔)
ホームページのバナー広告の収入でございますが、平成18年度につきましては約550万円の収入を上げております。
村山 祥栄
ありがとうございます。
この前、非常に何か厳しいようなことを京都新聞かどこかが書いていましたけども、550万、新たに収入が生まれたということは非常に喜ばしいことだと思っています。
このホームページのバナー広告についても、一つ御提言と言いますか、御提案致したいのは、実は、横浜市が非常にうまいこと広告収入を取っていく作業を今やっておりまして、特定の部署が一手に広告を引き受けるということをやっているんですけども、横浜市のホームページを見ますと、今、京都市は一つの入札でまとめてバナーを広告代理店にお売りされていると思うんですけども、横浜市のホームページは、各ページごとに、トップバナーは7万円です、12枠あります、先着順です、募集要項はこちらを御覧くださいという具合いに、ホームページの中で具体的に広告の募集を結構熱心にされています。
大体向こうでいきますと、今3,000万、18年度予算で予算計上されているんですけども、結構な収入になりつつあるのかなと。
具体的には、今現在京都市はトップページだけ広告を付けていらっしゃると思うんですけども、できれば各項目ごとに、ページをめくっていけばそれぞれ広告が入っているような形にすると非常にいいのではないかなということで、私、この前から思っていたんですけども、実は横浜市を見ていますと、既にやっておりまして、例えばホームページの頭の、皆さんが引っ越しますとか引っ越してきましたとかというのを調べたいときに見ますと、そこには不動産屋さんのページですとか、お寺のページですとか、新しいマンションの売出しとか、いろんな形で広告をされています。
これを見ていますと、例えば、横浜ですから都筑区のトップページ、中区のトップページとか各区役所ごとのページにも、それぞれ地域のお店がバナーをはられていたり、ごみの資源の分け方、出し方とか、粗大ごみのページに行くと、そういうたぐいのページに関連する業者さんが広告を出されていたりとか、こういう形にすると、かなりニーズも細分化されていきますから、非常に広告主としても出しやすい形になっていくんではなかろうかなという風に思うわけでございますけれども、こういったホームページを使って直接的に訴求をさせていくということと、もうちょっと細かく広告を落とし込んでいくことはできないのかなと思うわけでございますが、その辺のお考えはいかがでございましょうか。御所見を伺いたいと思います。
市長公室長(塚本稔)
ホームページのバナー広告でございますが、現在10社ほど広告が入っておりまして、非常に好評でございます。
委員御指摘のトップページだけじゃなくてそれぞれのページでもということでございますが、先週、交通局の方が、交通局のホームページでも広告をやっていきたいということをアクションプログラムで発表しておりますが、今後はトップページだけじゃなくて、それぞれのページの特性に合わせた広告も取れるように、ただ、飽くまで民間企業ではなくて、京都市という地方公共団体のホームページですので、その辺りも十分配慮しながら進めていきたいと考えております。
村山 祥栄
是非よろしくお願いしたいと思います。
私の方からは以上にしておきます。